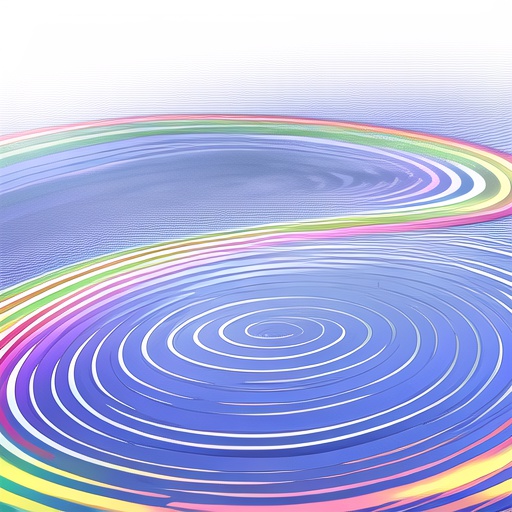コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- 心の不調と必要3条件
心の専門家とはどのような人でしょうか。一般の人とは何が違うのでしょうか。心へのアプローチ法によって答えはさまざまでしょう。しかしその答えをよく眺めてみると、心の専門家とは、「ある事柄の効果を最大化するために『必要なときに、必要なことを、必要なだけ』を速やかに考え対応できる人」ではないかと私は思います。心理検査を行う専門家は、検査時の行動を見極めたり心理検査結果を評価するだけでなく、「その検査を実施する適切なタイミング」「他にどのような検査が必要か」「検査を何回行うべきか」を判断できる能力を持っています。この考え方を私は「心の必要3条件」と呼んでいます。
この3条件への理解が十分でなかったり、各条件における選択を誤ると、心理的な混乱を招く可能性があります。例えば、「必要なとき」を誤ると、「すでに遅し…」「未来の自分はこんなもんじゃない!」といった空虚な気持ちに陥ることがあります。適切なタイミングを逃すリスクは計り知れません。「必要なこと」を誤ると、勘違いを生じさせる可能性があります。その結果、つい言い訳をしたり、他者と共有できない独自の持論を展開してしまい、関係性に悪影響を及ぼすこともあります。そして最後に「必要なだけ」を誤ると、執着が強くなりすぎたり、逆に無関心になりすぎたりすることがあるでしょう。
日常生活が穏やかで豊かに感じられる瞬間は、おそらく「心の必要3条件」が適切に機能しているときです。心の不調の多くは、この3条件が機能不全を起こしているときに生じるのかもしれません。 これは心の不調を見立てる方法のひとつです。
- 必要3条件の具体例
私たちは、日々「人が人を見立てる」体験をしています。裁判官のような法に沿って公平に人を評価する専門家もそのひとつです。しかし、裁判官でさえ一日中専門家であることは難しく、家庭では羽目を外すこともあるでしょう。日常生活ではこの「心の必要3条件」が働かない状況を楽しむ場面さえもあるのです。
例えば職場では、同期だった友人が急速に昇進し、上司となった状況を考えてみましょう。その上司は責任感から、書類の締め切りにこだわり、同僚に無理な仕事を押し付けます。今日は我が子の誕生日なのに残業を強いられる…。これは「必要なとき」のすれ違いが生じた典型例です。
学校場面では、「今日は塾があるので早く帰る必要があるが、友だちに誘われて遊びに行きたい」という葛藤が生まれることもあります。家庭では、「お父さんが帰りが遅い」「(母親から見ると)息子が宿題をせずにゲームばかりしている」「徹夜でゲームに没頭している」といった状況が見受けられることがあります。場合によっては家族の問題となることもあります。しかし家庭にはその家庭ならではのつながり方があるのです。
また、個人の内面でも「必要3条件」は作用します。たとえば「教師になりたい大学4年生が、理想と現実のギャップに悩み、教職受験に不安を感じて勉強に手がつかない」というケースがあります。この場合、「必要なとき」「必要なこと」「必要なだけ」の全てが課題となっており、条件をとらえ直すことが必要です。
- まとめ
ご安心ください。専門家でなくとも、「心の必要3条件」を意識することで、「今何が問題か」を理解する手助けになるかもしれません。 心を穏やかに保つためには、適切な自己への気づきが重要です。自分がどのような状態にあるかを理解することが、自己への気づきの第一歩なのです。
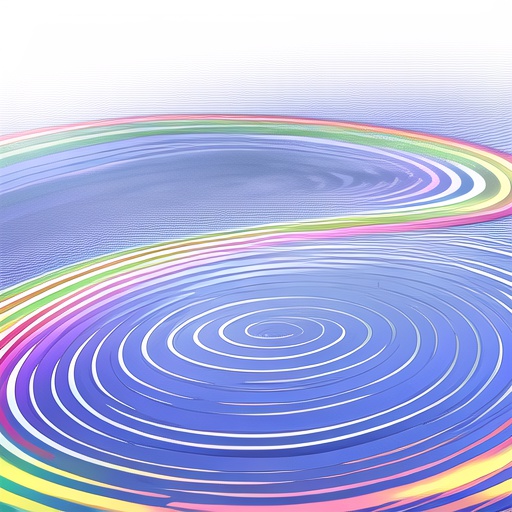
PAGE TOP